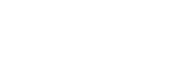札幌ではまだ雪の残る3月、京都研修旅行に連れていって頂きました。
京都はきっと、オンシーズンで満開の桜が見られると、ワクワクして出発しました。
桜はまだ蕾でしたが、外国人観光客がいっぱいで、有名な観光名所はどこも人でいっぱい…

そんな中、色々な 工房を見学させていただき、帯屋さんでお勉強してきましたので、今日はそれを書きたいと思います。
①西陣つづれ帯
つづれ帯一筋という浅田つづれという所に行きました。
「つづれ織」は話しでは、よく聞いてましたが、実際に爪つづれを織っている現場を見るのは初めてでした。

にんげんの手でこんな事ができるなんて‼
下絵に描かれた文様を、緯糸だけで、表現し、様々な色糸を用い、必要な部分だけに必要な色糸を織り込んでいくのです。
こうした文様はノコギリの歯のようにギザギザにした指頭の爪で丹念に丹念に糸をかき寄せ、織り込んでいきます。 まさにそれは、手わざを超えた「爪先の技」爪の先で一糸一糸織り込みながら文様にいきいきとした生命を与えるのです。
つづれ織りには、大変な根気と労力を要し、文様によっては、一日にわずか1センチしか織り進めないこともあるそうです。
気が遠くなるような、織りの工程に言葉もなく、感動した私達でした。

②つづれ織りの歴史
つづれ織りは約4千年前のエジプトに生まれたコプト織りが起源とされています。
古代エジプト、古代中国、南米のブレインカなど古代文明の遺跡から発見されています。
日本へは、シルクロードを通り、すでに奈良時代には伝えられていたようです。
奈良の正倉院や法隆寺の遺品として、いくつかが残されています。
そして、再び登場するのは、江戸中期のころ、京都西陣の井筒屋(林)瀬平が再興したといわれ、その後、一般にも盛んになったそうです。
ヨーロッパのつづれ織り~ゴブラン織りのタペストリーや中国の繊細で真に迫る文様表現が、織匠達の創作意欲を多いに刺激し本つづれ織り、西陣の地で江戸時代以来の技の本流を受け継ぎ、さらに磨きをかけているのですね。
③手織紋つづれ帯
もう一つ、紋型紙を使って、柄の部分にジャガードを使い、手機にて織りあげる手機紋つづれ織りの現場も、見学させていただきました。

大変な力を要する、作業で年配の3名の方々が、織っていましたが、熟練の技術が必要ということでした。
織る職人さんが、少なくなっていくこおとが、悲しいですね。

④つづれ織りの素晴らしさ
実際の作品の数々を見せていただきました。


ため息が出るほど素晴らしい‼
作る工程を見ているから、尚更、そう思いますよね。
ひと目、ひと目爪先で織り描いていく爪搔本つづれ織りは大変、手間がかかるものだけに、大部分がお太鼓と腹だけに柄を織り出した袋名古屋帯です。
しかし、静謐無比な柄と張りのある地風のつづれ帯は織物として最高に贅沢な逸品ですので、柄づけにより、留袖や訪問着からおしゃれ着まで幅広くあわせられます。
名古屋帯だけど、フォーマルまで締められる帯なんですよ!という、説明は何度か聞いていましたが、実物をみて納得をいたしました。
珍しく、お勉強したことを、長々と書いてしまいました…が、実は織っていらっしゃる方が、実際に都屋にいらっしゃる機会があるそうです。
実際に、見て、手に取って、織っていらっしゃる職人さんに、お話しを聞く!
絶好の機会がありますよ‼
皆様、お楽しみに‼
次回は6月位になると思いますが、続きをお話し出来たら、嬉しいです。
着物で京都をそぞろ歩き‼満喫いたしました。
皆様に感謝です。ありがとうございます!

「前結び」で新しい着物ライフを。
「花いち都屋」の着付教室は、帯を前で結ぶから初心者でも安心!
さらに、手や肩の負担を軽減するので、後結びが難しい方にも最適です。
ゴムを使った着付け方法は、軽くて快適と大好評!北海道内7店舗で無料体験教室開催中。
\詳しくはこちら/
私の過去の記事もご覧ください
令和7年 春 卒業式に向けてのコーディネート@花いち都屋着付教室講師 伊藤昌子
冬の札幌 着物で遊ぼう!!@花いち都屋着付教室講師 伊藤 昌子
夏だ‼祭りだ!浴衣で遊ぼう‼2024年夏@花いち都屋着付け教室講師 伊藤昌子
冬の札幌 きものでウォーキング@花いち都屋着付け教室講師 伊藤昌子
クリスマスは着物で❣ @花いち都屋本店 着付教室講師 伊藤昌子
芸術の秋を着物で楽しもう@花いち都屋着付教室講師 伊藤 昌子
着物でGO!!行ってきました!京都南座@花いち都屋着付教室講師 伊藤昌子
令和5年 今年の夏は浴衣で遊ぼう!!@花いち都屋着付教室 伊藤昌子
着物でGO!行って来ました!富士山と河口湖に行って来ました‼@花いち都屋着付教室講師 伊藤昌子
2023年 着付け教室でのよくある? ある?ある?@花いち都屋 着付け教室講師 伊藤昌子
私の着物遍歴(20代・30代・40代~)@花いち都屋着付教室講師 伊藤昌子
着物でGO 札幌で9月・10月におすすめのお出かけスポット@花いち都屋 着付教室講師 伊藤昌子
【札幌】夏のお祭と和のお稽古 今昔@花いち都屋着付教室講師 伊藤昌子
書道 楽しいカルチャー教室@花いち都屋着付け教室講師 伊藤昌子
茶道と華道 楽しいカルチャー教室@花いち都屋着付け教室講師 伊藤昌子
半襟付けも習える着付け教室/日舞教室(カルチャー教室)に通ってできないことができるように!!@札幌・花いち都屋 着付け教室講師 伊藤昌子